 |
 |
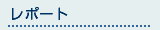
|
 |
���N�U������10���ɂ킽���čs����Ă����D��̕ł��B
|
| �Ă����D��@�ߘa4�N�i2022�j |
00�@2022/04/22�@2021�N�i�ߘa3�N�jtenngusa�^���V�T���i2021�N1���`2021�N12���j
01�@2022/03/10�@������1����D��
02�@2022/06/22�@��������1����D��
03�@2022/07/07�@������2����D��
04�@2022/07/11�@���Q����1����D��
05�@2022/07/14�@�����s��1����D��
06�@2022/07/28�@�郖����1����D��
07�@2022/08/19�@�a�̎R�����D��
08�@2022/08/24�@���茧���D��
09�@2022/08/26�@�O�d�����D��
10�@2022/09/08�@������3����D��
11�@2022/09/13�@���m�����D��
12�@2022/09/15�@��������2����D��
13�@2022/09/16�@���Q����2����D��
14�@2022/10/06�@������4����D��
15�@2022/10/21�@�郖����2����D��
16�@2022/11/10�@������5����D��
17�@2022/11/17�@�����s��2����D���@
|
 |
|
00�@2021�N�i�ߘa3�N�jtenngusa�^���V�T���i2021�N1���`2021�N12���j
�s���Y�e���O�T�i2022�N4��22�����݁j�t
�@2021�N�̍����e���O�T���D��́A3��11���̐É�����1����D���n�܂�A11��18���̓����s��2����D��������ďI�������B
�@�S�����Y�ʂ͓��D�O���ʂ��܂߂Đ���313�g���ƂȂ�A2020�N���Y�ʂ�73���i2020�N�S�����Y�ʁF429�g���j�Ƒ啝�Ɍ��Y�����B2017�N����450�g���O��Ő��ڂ��Ă������i2016�N��563�g���j�A2021�N�͑啝�Ɍ��Y�������ƂƂȂ�B
�@���Y�̌����Ƃ��āA�@�����̑�֍s�A�A�C���̉h�{���s���i�������C��ł͏t���Ɍ]���ނ��唭���A�h�{������悵���ׁA�h�{���s���ƂȂ����j�A�B�����{�n��`���C�n��ł̑����~�J����ɂ����n�����̌����i��B�k���n��F5/15�A���C�n��F5/16�j�����l������B
�@�啝�Ȍ��Y�͓��D��ł̗��D���i�ɑ傫���e�������B���ɓ�������1����D��̏o�i�ʂ�2020�N���19���ł������ׁA�w���������������ė��D���i�����������B�{���D��̗��D���i���A�������̓��D��ł̗��D���i�ɉe����^���A���ʂƂ��đS���I�ȗ��D���i�̍����Ɍq�������B�É����̐��Y�ʂ͑����������A�ߋ�5�N�ł݂�ƌ��Y�X���ł������B�܂��u�����h�i�ł��邱�Ƃ���A���D���i�͍��~�܂�̏�ԂƂȂ����B
�@2022�N�̐��Y�ʑ����Ɋւ��Ă͉��L�������������Ƃł��邪�A���i�K�ł̓e���O�T�������̏����i�K�ł���A���Y�ʂɂ��Č��y�͓���B���݂ɍ��N�i2022�N�j�J�Â��ꂽ���D��͌��i�K�ł͐É�����1����D��݂̂ł��邪�A�o�i�ʂ͍�N��88���ł������B�܂�4�����ɊJ�Â����啪����1����D���2021�N��1����D���45�����x�ł���B����Ő�t���Y�e���O�T�͌��i�K�ł͏����̎悳��Ă���B
�@ �E�q���������i1���`3���j�ɊC������13���i�`15���j�ȉ��ƂȂ邱�ƁB
�A �C���̉h�{�����L�x�ł��邱�ƁB
�B �e���O�T�������i4���`6���j�ɊC�������㏸���邱�ƁB
�C�@�e���O�T�̎掞���i4���`8���j�ɓV�ǂ����ƁB
�y�S���Y�n�ʁE���Y�ʁi���D��o�i�ʁ{���D�O���ʁj�z
|
| �Y�n�_�N |
�ߘa3�N
2021�N |
�ߘa2�N
2020�N |
�ߘa���N
2019�N |
����30�N
2018�N |
����29�N
2017�N |
����28�N
2016�N |
����27�N
2015�N |
| �����s |
19 |
40 |
35 |
34 |
42 |
35 |
44 |
| ���� |
47 |
41 |
48 |
69 |
90 |
110 |
111 |
| �O�d�� |
1 |
3 |
4 |
8 |
11 |
11 |
8 |
| �a�̎R�� |
22 |
14 |
19 |
16 |
14 |
12 |
9 |
| ������ |
12 |
34 |
36 |
36 |
31 |
36 |
26 |
| ���Q�� |
39 |
88 |
103 |
114 |
135 |
118 |
149 |
| ���m�� |
1 |
3 |
9 |
13 |
9 |
16 |
11 |
| ���茧 |
4 |
5 |
5 |
4 |
6 |
13 |
20 |
 |
| ��L�Y�n�v |
145 |
228 |
259 |
294 |
338 |
351 |
378 |
| �S�����Y�� |
313 |
429 |
458 |
411 |
471 |
563 |
486 |
|
�i���j�X�c���X�E�������
������l�^�P�ʁF�g���i�����_�ȉ��͎l�̌ܓ��j
�O�d���o�i�ʁi2021�N�j�E���m���o�i�ʁi2021�N�j��1�g���O��ׁ̈A�����_�ȉ����\���B
|
 |
|
�s�O���Y�e���O�T�i2022.4.22���݁j�t
�@�O���Y�e���O�T��2021�N�̔N�ԑ��A���ʂ�1,153�g���ƁA2020�N�̗A���ʂƔ�r����80���ƌ��������i2020�N1,433�g���j�B2017�N�����5�N�Ԃł݂Ă��ł����Ȃ��B���ϗA�����i�͑O�N��83���ƂȂ�A2017�N�����5�N�Ԃł���r�I�����ƂȂ����B
�@�؍��Y�e���O�T��2021�N���A���ʂ�182�g���ƁA2020�N�̗A���ʂƔ�r����70���ƌ��������i2020�N260�g���j�B2017�N�����5�N�Ԃł݂�Α������J��Ԃ��Ă��邪���Ȃ����Ƃ�����B�A�����i�͑O�N��87���ƂȂ�A2017�N�����5�N�Ԃł���r�I�����ƂȂ����B�����2019�N�Ɋ؍����ł�3�N�Ԃ̍��l���t�_�I�����A�V�����W�J�ƂȂ����ׂƎv����B
�@�����b�R�Y�e���O�T��2021�N���A���ʂ�637�g���ƁA2020�N�̗A���ʂƔ�r����112���Ƒ��������i2020�N��569�g���j�B2021�N�̑�����2020�N�ł̗A���ʂ����Ȃ������ׂƍl������ׁA2017�N�����5�N�Ԃł݂�Ƒ������J��Ԃ��Ă��邪���ϓI�ȗʂƂ�����B�A�����i��80���ƂȂ�A2017�N�����5�N�Ԃł���r�I�����ƂȂ����B
�@���i�K�ł͉~���X���ƌ������̉e�����X�ɋ��܂�A2022�N�̍w�����i�͏㏸����Ɨ\�����Ă���B�؍��ł͐l������㏸���Ă��邱�Ƃ���A���̌X�������܂�Ɨ\������B
�y�N�ԗA���ʁz
|
|
�ߘa3�N
2021�N |
�ߘa2�N
2020�N |
�ߘa���N
2019�N |
����30�N
2018�N |
����29�N
2017�N |
| �A������ |
1,153 |
1,433 |
1,731 |
1,627 |
1,630 |
| �؍� |
182 |
260 |
181 |
271 |
535 |
| �����b�R |
637 |
569 |
802 |
681 |
519 |
|
�����Ȗf�Փ��v���i�P�ʁF�g���j
|
|
�s���V�i2022.4.22���݁j�t
�@�V�R�����V�̐������Ԃ͎��12���`2���ł���A�V��ɑ傫�����E�����i��Ԃ̗₦���݂ƒ��Ԃ̓��Ǝ��Ԃ��d�v�@��1�j�B������12����{�̗₦���݂��ォ�����ׁA�����J�n���x�ꂽ��A�N�������Ⴊ�x�X�������āA���Ǝ��Ԃ����������B���̌��ʁA�V�R�����V�̐������Ԃ��Z���Ȃ�A���Y�ƂȂ����B�N�Ԑ��Y�ʁi��2�j��2021�N��91�g���i����j�ƂȂ�A2020�N�Ɣ�r����87���ƌ��Y�����i2020�N104�g���i����j�j�B
�@�p���V��65�g���i����j�ƂȂ�A2020�N���Y�ʂƔ�r����87���ƌ��Y�����i2020�N75�g���i����j�j�B����������V�Ɠ��l�V��̉e�������ׂƍl������B
�@2021�N���V�A���ʂ�1,603�g���ƂȂ�A2020�N�A���ʂƔ�r����102���Ɨ����ʂł������i2020�N1,578�g���j�B���ϗA�����i�͑O�N��101���ƂȂ�A�������i�ł������B
�@���i�K�ł́A�~���X���ƌ������̉e�����X�ɋ��܂�A�e���O�T���l��2022�N�̍w�����i�͏㏸����Ɨ\�����Ă���B�؍��ł͐l������㏸���Ă��邱�Ƃ���A���̌X�������܂�Ɨ\������B
��1�F�Ⓚ�������J��Ԃ��Đ�������ׁB
��2�F�Ⓚ�ɂ�ۗL���Ă���H��͉Ċ������Y����B
���Y���V�F�i���j�X�c���X�E�������
�A�����V�F�����Ȗf�Փ��v���
|
 |
|
01�@2022/03/10�@������1����D��
|
|
�@�É�����1����D���N�Ɠ�������3����{�ɊJ�Â��ꂽ�i3��10���j�B�{���D�2022�N���D��̍ŏ��ł���A�É������D��̓���������Â���B����ŐÉ����e���O�T�̓u�����h�e���O�T�Ƃ��ėL���ȈׁA�S���̓����܂ł͌���Â��Ȃ��B
�@�o�i�ʂ�6,075kg�ƁA��N�������Ɣ�r����88���̌��Y�����i2021�N���D��F6,875kg�j�B�ߋ�5�N�Ō��Ă��ł����Ȃ��ʂł���i���j�B���t�̕��X�ɘb���f���Ă��A��ʂɃe���O�T�͕t�����Ă��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������B���N�͋C�����Ⴉ�����ׁA�E�q�̕t�������҂����Ƃ���ł��������c�O�ł���B
�@�ʏ�ʂ�A�O���Ɉɓ��ɓ����Ċe�Y�n�̃e���O�T��Ԃ��m�F�����B����͏����c�Ɛm�Ȃł���B��������̃e���O�T���Y��ɎN���H�����{����Ă���A�ٕ������Ȃ������B����͊����l�ł������B���̎Y�n�͂���܂ł������̒l�i�ŗ��D����Ă���A���ꂪ�̎�Ǝ҂̍̎�ӗ~�ƑI�ʈӗ~�̌���Ɍq�����Ă���悤���B�A�I���t�������������Y��ɎN���Ύg�p�\�Ǝv��ꂽ�B�H�v������낢��g�p���@�͌�������̂��B
�@���D�Ǝ҂�7�ЁB���AFAX���D��3�ЁB���̃R���i�Ђɂ����Či�C�������Ă��銴�����������A�ɓ��Y�e���O�T�̓u�����h�Ƃ��ėL���ł���A�X�Ɍ��Y���Ă���ׁA�ɒ[�ɉ��i�������邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv��ꂽ�B���ہA�J�[�����ƁA����܂ł̗��D���i�܂������i�ƂȂ����B
��1�F2016�N17,225kg�A2017�N15,950kg�A2018�N8,650kg�A2019�N7,200kg�A2020�N6,751kg�A2021�N6,875kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 ���P���E�[�i ���P���E�[�i
 ���ؑ�E�e���O�T�̎�n ���ؑ�E�e���O�T�̎�n

���P��

�m�Ȃ̓X�����C�J���L��
|
 |
 |
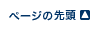 |
 |
|
02�@2022/06/22�@��������1����D��
|
|
�@��������1����D���N�Ɠ�������6�����{�ɊJ�Â��ꂽ�i6��22���j�B�{���D��S���A��Â̓��D��ł͍ŏ��ƂȂ�A3���̐É������D��Ɠ��l�A2022�N�̓��D��̕����������܂�B
�@�o�i�ʂ�5014.2kg�ƁA��N�������Ɣ�r����14�����Y�����i2021�N���D��F4,377kg�j�B��������N��20�g���O��o�i����Ă���ׁi���j�A�������N�Ɉ��������������Ă���Ƃ�����B
�@���������D��͓암�n�悩�瑽���o�i�����X���ɂ��邪�A���N�͖k���n�悩��̏o�i���ڗ������B�܂��k���n��̓J�L�������t������X���ɂ��邪�A���N�͕t�������Ȃ��A�Y��ȗl���ł������B�����̕��̘b�ł͊C�����������X��������Ƃ̂��ƁB�o�i�ʂɂ����āA�암�����Ȃ��k���������Ƃ������Ƃ́A�암�̊C�������e���O�T�ɂƂ��č����A�k���̊C�������e���O�T�ɂƂ��ēK���ł������\��������B�܂��A�J�L�t���ɂ��Ă��C�������e����^���Ă���\��������B
�@���D�Ǝ҂�8�ЁB���N����N���l�A�o�i�ʂ����������ׁA�����͌������邱�Ƃ��\�z���ꂽ�B���ہA���D���i�͍����������A�グ���͗\�z�ȏ�ŁA��N�̗��D���i����X�ɏ�ς݂��ꂽ�`�ƂȂ����B���ɃJ�L�̕t�������Ȃ��A�o�i�ʂ̑����k���n��̍w���������������Ă��Ȃ荂�������B����̗��D���i���������Q�����D��e����^����Ǝv����B
���F2017�N18,200kg�A2018�N16,117kg�A2019�N21,866kg�A2020�N22,960kg�A2021�N4,377kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 �������Y�e���O�T �������Y�e���O�T
�o�i�ʂ����Ȃ��ׁA���ςƂȂ��Ă���B
 ���������A�E�O�� ���������A�E�O��
�~�J�̍��Ԃ̐����
 ��C�����琼��]�ށB ��C�����琼��]�ށB
�������k���ɂ�����n��͉��₩�ȊC��
 ��勴�Ɩ�C�� ��勴�Ɩ�C��
�������k���ɂ�����n��͉��₩�ȊC��ł��邪��C���͂��Ȃ�C���������B
|
 |
 |
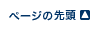 |
 |
|
03�@2022/07/07�@������2����D��
|
|
�@�É�����2����D���N�Ɠ�������7����{�ɊJ�Â��ꂽ�i7��7���j�B�o�i�ʂ�7,392kg�ƍ�N�������Ɣ�r����12�����Y�����i2021�N���D��F8,365kg�j�B
�@7����{���̗v�o�i�ʂ�13,467kg�ƍ�N�Ɣ�r����12�����Z���Ă���i2021�N���D��F15,240kg�j�B�ߋ�5�N�ł݂�ƁA2017�N�`2019�N��20,000kg�ȏ�o�i����Ă����ׁA�������N�͌������Ă���Ƃ�����i���j�B
�@������O���Ɋe�Y�n�i�����c�A�m�ȁA�{��A���j���������Ē������B�N���H�i�͂����ʂ�ǂ��I�ʂ���ăJ�L��ٕ������Ȃ��A�N�����X�ł������B�ԑ����ǂ��I�ʂ��s���͂��Ă����B�I�ʂ���Ă��錻����������Ē������Ƃ���A��͂�ǂ��I�ʂ���Ă���A���ꂪ���i�Ɍq����̂��Ɗ������B�܂��A�����t�����e���O�T�̏�Ԃɂ�苙���̕������m�ɕt�����Ă���ׁA���D����Ǝ҂��������₷���B�O�ҁi�̎�Ǝҁ^�����^���D�Ǝҁj�̒��a�����܂��Ƃ�Ă���̂ł͂Ɗ������B
�@���D�Ǝ҂�6�ЁB���AFAX���D��1�ЁB�������̑匸�Y�Ɍ�����悤�ɁA�S���I�Ɍ��Y�̌��O���l����ꂽ�B�ɓ��e���O�T������ɊY�����Ă���A�X�Ɉɓ��Y�e���O�T�̓u�����h�Ƃ��ėL���ł���̂ŁA���i�������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����Ǝv��ꂽ�B���ہA���D���i�͂���܂ł̗��D���i���Q�l�ɂ������i�ƂȂ����B
��2017�N45,225kg�A2018�N25,490kg�A2019�N25,400kg�A2020�N13,047kg�A2021�N15,240kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 ��c��������m�Ȃ̊C��]�ށB ��c��������m�Ȃ̊C��]�ށB
 �{�苙�` �{�苙�`
 �{��̕��X�̃e���O�T�I�ʍ�� �{��̕��X�̃e���O�T�I�ʍ��
 ���ɓ��̊C�ݐ��i�O�Y�E�{����ʁj ���ɓ��̊C�ݐ��i�O�Y�E�{����ʁj
 ���l�C�݂�������ʂ�]�� ���l�C�݂�������ʂ�]��
|
 |
 |
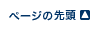 |
 |
|
04�@2022/07/11�@���Q����1����D��
|
|
�@���Q����1����D���N�Ɠ�������7����{�ɊJ�Â��ꂽ�i7��11���j�B�o�i�ʂ�52,505kg�ƍ�N�������Ɣ�r����169���Ƒ��Y���Ă���i2021�N���D��F31,093kg�j�B�S���I�Ȍ��Y�X���̒��ł̑��Y�A�����50,000kg�������Ƃ͊�������Ƃł���B���Q���͎l���̒��ł͖k�̕��ł���A�������ł��k���n�悪���Y�����ׁA���l�̗v���i�����̗��ꓙ�j�����邩������Ȃ��B�������A�ߋ�5�N�Ŕ�r����Ə��Ȃ����ł���i���j�A����܂łƂ͍��{�I�Ɋ����قȂ��Ă���\��������B
�@�����FAX���D�ׁ̈A�e���O�T�̗l���̓T���v���Ɠ���Ŋm�F���邱�ƂƂȂ����B���̕��@�ł��e���O�T�̗l�����悭�c���ł���ׁA���A�̕��X�̑Ή��ɂ͊��ӂ���Ƃ���ł���B
�@���ۂɊm�F����ƁA��͂萣�˓��C���̃e���O�T�͓��C�̓����A�L�㐅�����̃e���O�T�͊O�C��̓����������Ă����B�܂��A��������̖����͂悭�I�ʂ���Ă���A�t�P��ٕ��A�J�A�^�����̍��������Ȃ������B�É������D��l�A�����Ǝ��ۂ̗l�������v����Ɠ��D�Ǝ҂����D���₷���B���݂Ƀg���N�ɂ��Ă͐Ԃ̊ܗL�����e�����ňقȂ��Ă����ׁA�����̉��i�œ��D���邱�ƂƂȂ�B
�@���D�Ǝ҂�7�ЁB����̈��Q�����D��͑��Y�������A���������D��̗��D���i����e������B���������D���2�N�A���̑匸�Y�ō��������ׁA���Q�����D��ł͑��Y�������D���i�͍�N���݂Ɨ\�z���ꂽ�B���ہA�J�[�����Ƃ�͂藎�D���i�͍�N���݂ł������B
��2017�N102,042kg�A2018�N91,925kg�A2019�N82,966kg�A2020�N68,342kg�A2021�N31,093kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 |
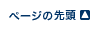 |
 |
|
05�@2022/07/14�@�����s��1����D��
|
|
�@�����s��1����D���N�Ɠ�������7����{�ɊJ�Â��ꂽ�i7��14���j�B�o�i�ʂ�6,832kg�ƍ�N�������Ɣ�r����91���Ǝ���Y�����i2021�N���D��F7,500kg�j�B�������A2017�N����2020�N�����Ă�10,000kg�ȏ�o�i����Ă���ׁi��1�j�A���ۂ̂Ƃ���A���Ȃ茸�Y���Ă���Ƃ�����B
�@�����֍s�̒��S�����ֈڍs�������Ƃ�i��2�j�A�l���k���n��ł̑��Y�Ɠ암�n��ł̌��Y�����Ă���ƁA��͂�C�����ω���h�{���ω��������ł͂Ȃ����ƍl������B
�@�����������ɑ��A���A�ł͋ߔN�̌��Y�ɑ���ӌ�������J����A�������c���Y�����b������ꂽ�Ƃ̂��ƁB�܂������s���A�ł�2020�N�`2022�N���̈ɓ������̊C�����ɂ��ēZ�߁A��������Ă����B���������������������������Ă����ƐɊ肤�B
�@���D���ł͎��ۂ̃e���O�T���m�F�����B���̎����ɍ̎悳�ꂽ�e���O�T�̓J�L�̕t�������Ȃ��A�����܂肪�ǂ��B�X�ɍ̎�Ǝ҂̕��X���Y��ɑI�ʂ��Ă���ׁA�A�I�Ƃ��������ł����Ă��A�I�̊ܗL�������Ȃ��e���O�T�������B
�@�܂��A�ɓ��哇�̒��ł����c�n��Ɣg���n��ł̓e���O�T�̗l�����قȂ�B���c�n��͈ɓ������̑Ί݂Ŕ�r�I���₩�ȊC��i�ɓ��哇�̒��ł́j�A����Ŕg���n��͊O�m�ɖʂ���C����g�������C��ł���B���ׁ̈A�����P�O�T�Ƃ��������ł����Ă��A���c�n����g���n��̕��������e���O�T�������ܗL����X���ɂ���B���ɗD��͂Ȃ��A�e�X�K�����g�p���@������A�K�v�ɉ����ē��D���Ă����B
�@���D�Ǝ҂�8�ЁB�����s�Y�e���O�T�͈ɓ��������Y�n�Ƃ���ׁA�ɓ��u�����h�i�ł���i��3�j�B���ׁ̈A�u�����h���i�ɂȂ�X�������邪�A�X�ɍ���̌��Y���w������������������ƍl����ꂽ�B���ہA�J�[�����ƐÉ������D��i�ɓ����D��j�Ɠ����ȏ�̍��z���D�ƂȂ����B���̌X���͏o�i�ʂ���������܂ő����̂ł͂ƌ��O���ꂽ�B
��1�F2017�N11,881kg�A2018�N14,263kg�A2019�N13,104kg�A2020�N16,350kg�A2021�N7,500kg�A2022�N6,832kg
��2�F�����s������_�ѐ��Y�����Z���^�[HP
��3�F��ʓI�Ȉɓ��u�����h�Ƃ��āA�ߐ����ɂ�����ɓ����i�ɓ������ƈɓ������j�������g�p�����B
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 �ۊǂ���Ă���e���O�T �ۊǂ���Ă���e���O�T
 ���D��� ���D���
 ���ƂȂ��Ă��Ă��A�A�I�̊ܗL�ʂ͏��Ȃ��B ���ƂȂ��Ă��Ă��A�A�I�̊ܗL�ʂ͏��Ȃ��B
 �g���͊O�m���ׁ̈A�P�O�T�ł����߂������B �g���͊O�m���ׁ̈A�P�O�T�ł����߂������B
 ���c�͔�r�I���₩�ȊC��ׁ̈A�P�O�T����̂ƂȂ�B ���c�͔�r�I���₩�ȊC��ׁ̈A�P�O�T����̂ƂȂ�B
|
 |
 |
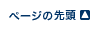 |
 |
|
06�@2022/07/28�@�郖����1����D��
|
|
�@�郖����1����D�7�����ɊJ�Â��ꂽ�i7��28���j�B�o�i�ʂ�1,702kg�ƍ�N�������Ɣ�r����80���ƌ��Y�����i2021�N���D��F2,126kg�j�B2017�N����̏o�i�ʂł݂��20,000kg�ȏ�̂��Ƃ����������ׁi��1�j�A��N��茸�Y���Ă���Ƃ�����B
�@�郖���͈ɓ��哇�ƊC�悪�߂��A�l�����A�����Ŏ��Ă���B�������A�o�i�ʂ͈ɓ��哇�Y�e���O�T�i�����s�Y�e���O�T�j���͌��Y���Ȃ������B�C��Ō���A�郖���C��E�ɓ��哇�C�拤�ɊO�m�n�̊��ł��邪�A�郖���͖[�������ƈɓ������ɋ��܂�Ă���B�����̉e�����قȂ�A���ʂƂ��ďo�i�ʂɉe�������ꂽ��������Ȃ��B
�@�郖���Y�e���O�T�̓A�����ł���ƑO�q�������A��P�O�T���������Ă���B�{�e���O�T���g�p���ăg�R���e��������ƃA�������L�̍d���݂̂łȂ��A�P�O�T���L�̔S���������B���̂悤�ȓ������D�܂����ɂ͎g���₷���e���O�T�ł��낤�B
�@���D�Ǝ҂�5�ЁB��N�͌��n�Ńe���O�T���m�F���邪�A�����FAX�œ��D�����B���D���i�͈ɓ��哇�Y�e���O�T�i�����s�Y�e���O�T�j�̗��D���i���Q�l�ɂ���邪�A���N�̈ɓ��哇�Y�e���O�T�̓��D��i�����s���D��G7/14�j�͏o�i�ʂ����Ȃ����������B���ׁ̈A�郖���Y�e���O�T������ɏ�����ƍl�����A���ہA��N�x�̓��D���i���������l�ŗ��D���ꂽ�B
��1�F2017�N2,360kg�A2018�N780kg�A2019�N2,514kg�A2020�N3,044kg�A2021�N2,126kg�A2022�N1,702kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 �郖���ƈɓ��哇�̈ʒu�W �郖���ƈɓ��哇�̈ʒu�W
|
 |
 |
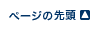 |
 |
|
07�@2022/08/19�@�a�̎R�����D��
|
|
�@�a�̎R�����D���N�ʂ�8�����{�ɊJ�Â��ꂽ�i8��19���j�B�o�i�ʂ�11,158.6kg�ƍ�N�o�i�ʂƔ�r����82���ƌ��Y�����i2021�N���D��F13,631kg�j�B�o�i�ʂ�2019�N���s�[�N�Ɍ������Ă��邪�A2017�N��13,790kg�A2018�N��15,863kg�A2019�N��18,872kg�ƈ�U���Y���Č��Y���Ă���A�o�i�ʂɂ͔g������i��1�j�B��T�Ɍ��Y�������Ă���Ƃ͂����Ȃ��B
�@�Y�n�ʂł����Ζk���̉����n�悪9,175kg�ƑS�̂�82������߂Ă���A�ߔN�͂��̌X���������Ȃ��Ă���i��2�j�B�����n��̃e���O�T�͓��p�̓������������e���O�T�ł���A�S�肪��̂ƂȂ�e���O�T�ł���B����ŋ��{�t�߂̓암�̃e���O�T�͒e�͂���̂ƂȂ�e���O�T�ł���B�ǂ���̒n����D�܂�邨�q�l�݂͂���ׁA�a�̎R�S��ő��Y���Ă������Ƃ����҂������B
�@�a�̎R�ɂ͑O�����肵�āA�����ɏh�������B�����̊C�̍���͈ɓ��̊C�̍���Ƃ͈قȂ�A��̍��肪�����C�������B�����͓��p���ɋ߂��A�ɓ��͊O�m���ɋ߂��ׁA���̈Ⴂ���C�̍���ɂ����ꂽ�̂��낤���B�O�m���ɋ߂����{�t�߂̊C�̍���͂ǂ��Ȃ̂��낤���B
�@�e�Y�n�̃T���v���͓��D����Ɋm�F�������B����n��ł̓J�L�̕t���ʂ�ٕ������ʂ������Ȃ��Ă���A�C�m���̕ω�������̂ł͂Ǝv��ꂽ�B���N�͎l���ł��k���̏o�i�ʂ��������A�암�̏o�i�ʂ��������Ă���ׁA�����̈ʒu����N�ƈقȂ�A�e����^���Ă���̂��B
�@���D�Ǝ҂�6�ЁB���AFAX���D��2�ЁB��N�̓��D�Ǝ�8�Ђł������ׁA�o�i�ʂ̑����k���n��̍w�������͎�a�炮�̂ł͂Ɨ\�z���ꂽ�B����ŁA�o�i�ʂ̏��Ȃ��암�n��ł͑R�����D���i�͉�����Ȃ��Ɨ\�z���ꂽ�B���ہA�J�[�����Ɨ��D���i�͂��̌X���ƂȂ����B
��1�F2017�N13,790kg�A2018�N15,863kg�A2019�N18,872kg�A2020�N14,374kg�A2021�N13,631kg�A2022�N11,159kg
��2�F�����n��̏o�i�ʂ̊���
2017�N34���A2018�N24���A2019�N58���A2020�N71���A2021�N86���A2022�N82���B
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 �����C�݂̗[���@ �����C�݂̗[���@
 �����C�݂̗[���A �����C�݂̗[���A
 �����C�݂̗[���B �����C�݂̗[���B
 �Ẳ_�����������̉����C�� �Ẳ_�����������̉����C��
|
 |
 |
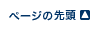 |
 |
|
08�@2022/08/24�@���茧���D��
|
|
�@���茧���D���N�ʂ�8�����{�ɊJ�Â��ꂽ�i8��24���j�B�o�i�ʂ�1,086��r����109���Ǝ���Y�����i2021�N���D��F1000kg�j�B2017�N����̏o�i�ʂł݂�ƁA2017�N��3,000kg�ȏ�ł��������A����ȍ~��1,500kg�O��ő傫�ȕϓ��͂Ȃ��i��1�j�B�����m���̎Y�n�͍����̉e����傫���邪�A����͍����̉e����R���Ȃ��̂ł��낤�i�Δn�C���̕����e�����₷���̂��j�B
�@��N�ɑ����A�����FAX���D�ƂȂ����ׁA���O�ɃT���v���𑗂��Ē������B�m�F����ƃJ�L�̕t���ʂ͏��Ȃ��Y��ȃe���O�T�����������B�܂��A����ł͖ѐ悪�ׂ������x�������Ȃ�e���O�T�i����ł͒j�V�ƌĂԁj����������X�������邪�A����̓}�N�T�i����ł͏��V�ƌĂԁj����̂ł������B
�@���D�Ǝ҂�5�ЁB�o�i�ʂ͏��Ȃ����A�^�����̏��o������Ă���ƁA�w�������͌������Ȃ��̂ł͂ƍl����ꂽ�B���ہA��N�x���D���i�Ɨ������ŗ��D���ꂽ�B
��1�F2017�N3,278kg�A2018�N1,322kg�A2019�N1,613kg�A2020�N1,814kg�A2021�N1,000kg�A2022�N1,086kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 |
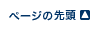 |
 |
|
09�@2022/08/26�@�O�d�����D��
|
|
�@�O�d�����D���N�ʂ�8�����{�ɊJ�Â��ꂽ�i8��26���j�B�o�i�ʂ�3,215kg�ƍ�N�o�i�ʂƔ�r����231���Ƒ��Y�����i2021�N���D��F1,390kg�j�B�������A2021�N�͍����̉e������1,390kg�Ƒ匸�Y�����ׁA��T�ɑ呝�Y�����Ƃ͂����Ȃ��B2019�N�A2020�N�ł݂��3,000kg�O��ׁ̈A��N���݂Ƃ������Ƃ���ł��낤�B���݂�2017�N�A2018�N�̏o�i�ʂ�10,000kg�O��ł������ׁA���̍��̏o�i�ʂɖ߂��Ă��炦��Ɗ肤�i��1�j�B
�@��N�ɑ����A�����FAX���D�ƂȂ����ׁA���O�ɃT���v���𑗂��Ē������B�m�F���Ă݂�ƃJ�L�̕t���͑S�̓I�ɑ����悤�ł��������A�����������肵���e���O�T�����������B�܂��A�e���O�T�����ۂɎϏn���Ă݂�ƁA�[���[���x��S�x�͍����l�ƂȂ����B���ׁ̈A����o�i�����e���O�T�͗ǎ��ł���Ɣ��f�ł����B�N�e���O�T���Y��ɎN����Ă���A������̔��ɓK���Ă����B
�@���D�Ǝ҂�6�ЁB���N�͘a�̎R���암�̃e���O�T�i���{�t�߁j�⓿�����̃e���O�T�̏o�i�ʂ����Ȃ��A���������̎O�d���Y�e���O�T�͍w����������������ƍl����ꂽ�B���ہA�J�[�����ƍ�N�̗��D���i�������z�ŗ��D���ꂽ���������������B
��1�F2017�N11,023kg�A2018�N8,256kg�A2019�N3,675kg�A2020�N2,598kg�A2021�N1,390kg�A2022�N3,215kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 |
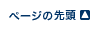 |
 |
|
10�@2022/09/08�@������3����D��
|
|
�@�É������D���N�ʂ�9����{�ɊJ�Â��ꂽ�i9��8���j�B�o�i�ʂ�6,972kg�ƍ�N�o�i�ʂƔ�r����67���ƌ��Y�����i2021�N���D��F10,409kg�j�B9����{���̗v�o�i�ʂ�20,439kg�ƍ�N�Ɣ�r����69�����Z���Ă���i2021�N���D��F25,649kg�j�B�ߋ�5�N�ł݂Ă�2017�N�`2019�N��20,000kg�ȏ�o�i����Ă����ׁA�������N�͌��Y�X���Ƃ�����i���j�B
�@��͂茸�Y���Ă��闝�R�͍����̎֍s���l������B�����A���n��ł͓�k�Ő��Y�ʂ��قȂ��Ă��邪�A�ɓ��ł͓��ɓ�k�Ő��Y�ʂ̈Ⴂ�͑R�������B���ɓ��n��͍����̉e���ڎՂ��ׁA�����̊C�������e����^���Ă��邩������Ȃ��B���N�͏����Ȃ�̂������A�C�����̏㏸�����������̂ł��낤���B
�@�e�Y�n������ăe���O�T���m�F�����B����Y�n�ł̓g���N�Ƃ����Ă��ԃg���ɋ߂��l���̃e���O�T���������B�N���H�҂Ɖ�X�Ǝ҂̊��o�̈Ⴂ�Ƃ͎v�����A���������N���H���Ē�����A���D����Ǝ҂��g�����肪�ǂ��Ɗ������B�܂���N�����A�I��J�L�������t�������Y�n���������B
�@���D�Ǝ҂�7�ЁB���AFAX���D��1�ЁB����̓��D��ɏo�i�\��̗ʂ̏����L��A����D�l�ɉe����^���邩�Ƃ��v��ꂽ���A���ۂ̗��D�l�͑z��ȏ�̍��l�ł������B��͂�o�i���ꂽ���ɗ��D���Ă��������ǂ��Ƃ̔��f�����������̂ł������̂ł��낤�B�É������D��͎c��2���\�肵�Ă��邪�A���̌X���͑����������B
��1�F2017�N58,075kg�A2018�N35,638kg�A2019�N30,281kg�A2020�N20,595kg�A2021�N25,649kg�A2022�N20,439kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 ���J�ɕ����ԓ����� ���J�ɕ����ԓ�����
 ���G�Ȓn�`���ǎ��̃e���O�T����� ���G�Ȓn�`���ǎ��̃e���O�T�����
�i�������j
 �e���O�T��������ʂ����C �e���O�T��������ʂ����C
�i�{��E�ܖ؍�j
 ���̕t�߂͒���ߗ������B���Ă��� ���̕t�߂͒���ߗ������B���Ă���
�i�{��E�ܖ؍�j
 �O�m�ցi�{��E�ܖ؍�j �O�m�ցi�{��E�ܖ؍�j

�W�u���ɏo�Ă������ȓ���
�i�{��E�ܖ؍�j
|
 |
 |
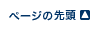 |
 |
|
11�@2022/09/13�@���m�����D��
|
|
�@���m�����D�9�����{�ɊJ�Â��ꂽ�i9��13���j�B�o�i�ʂ�106.1kg�ƍ�N�o�i�ʂƔ�r����18���Ƒ匸�Y�����i2021�N���D��F602.2kg�j�B2015�N����2019�N����10,000kg�O��Ő��ڂ��Ă������A2020�N����}���Ɍ��Y�����߂Ă���i���j�B����̏o�i�ʂ����O�����B�����C��̓������i�암�j��a�̎R���i�암�j�ł���N���猸�Y���Ă���ׁA���̊C��̊����ω����Ă���̂ł͂ƍl����ꂽ�B
�@���N���o�i�ʂ����Ȃ������ׁAFAX���D�ƂȂ����B���O�ɑ��t���Ē������T���v�����m�F����ƁA�o�i�ʂ͌������Ƃ����ǁA�N���H��͏�X�ŗL��A�T���N�T����N�ʂ�̗l���ł������B
�@���D�Ǝ҂�4�ЁB�ʏ�A�o�i�ʂ����Ȃ��Ɨ��D�����͌�������B�������A����͏��Ȃ������ׁA���D�ł��Ă��^�����ō��l�ƂȂ��Ă��܂��ꍇ���l����ꂽ�B�X�ɓ��D�Ǝ҂����Ȃ������ׁA�R���������Ȃ��Ǝv��ꂽ�B���ہA���D���i�͍�N�Ɠ����ł������B
���F2015�N7,729kg�A2016�N10,683kg�A2017�N8,975.8kg�A2018�N10,989.5kg�A2019�N7,607.9kg�A2020�N1,857.7kg�A2021�N602.2kg�A2022�N106.1kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 |
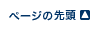 |
 |
|
12�@2022/09/15�@��������2����D��
|
|
�@��������2����D�9�����{�ɊJ�Â��ꂽ�i9��15���j�B�o�i�ʂ�5,372kg�ƍ�N�������̏o�i�ʂƔ�r����72���ƂȂ����i2021�N���D��F7,467kg�j�B�N�ԏo�i�ʂł�10,386kg�ƍ�N�Ɣ�r����88���ƂȂ����i2021�N�N�ԏo�i�ʁ�11,844kg�j�B�ꌩ�A�ʏ�̑����͈͓��Ɍ����邪�A2015�N����2020�N����30,000kg�ȏ�o�i����Ă���A����Ɣ�r�����30���O��̏o�i�ʂł���B����2�N�A�匸�Y���Ă���ƌ��킴������Ȃ��i��1�j�B�����C��̍��m����a�̎R���i�암�j�ł��匸�Y���Ă���ׁA���̊C��̊����ω����Ă���̂ł͂ƍl������B�S���I�Ȍ��Y�́A�����̒��S�����Ɉڍs���Ă���ׂƍl�����邪�A�����E���m�E�a�̎R�̊C��͑��C����������X���������ׁA�����֍s�ȊO�̗v��������̂ł͂Ȃ����B���݂ɖk���n��̃e���O�T�͑�1����D��ł̓J�L�t���ʂ����Ȃ��A����̑�2����D��ł͑��������B�J�L�͊C�����������Ȃ�ƕt�����₷���Ȃ�ׁA���N�͊C�����̏㏸�������x�������̂͂Ȃ����B
�@�{���D��͌��n�J�Âׁ̈A�O�����肵�ďo�i�����e���O�T���m�F�����B���̎����ɏo�i�����e���O�T�́A��N�Ċ��ɍ̎悳�ꂽ�e���O�T�ׁ̈A�J�L�̕t���������Ȃ�B������S�̓I�ɃJ�L�t���������������A�암�n��̂���Y�n�ł͊����J�L�t���ʂ����Ȃ������B�܂��A����Y�n�ł͏t���ɍ̎悳�ꂽ�e���O�T���o�i���ꂽ�ׁA�J�L�t���ʂ͏��Ȃ������B����ō̎�Ǝ҂���������Y�n�ł̓e���O�T�̗l���ɍ����������ׁA�Ȃ�ׂ������̃T���v�����m�F�����B
�@���D�Ǝ҂�8�ЁB���AFAX���D��2�Ђł������B���ɏq�ׂĂ͂��邪�A�ʏ킱�̎����̃e���O�T�̓J�L�t���������A��1����D��������ꂪ������₷���B�������A��1����D��ł̏o�i�ʂ͏��Ȃ������ׁA�ǂ̒��x�܂ʼn����邩�̌��ɂ߂��d�v�ł������B���ʁA�e���O�T�͂܂����v������ƍl���A�R������͉�����Ȃ��Ɨ\�z�����B���ہA�J�[�����O�D�l����͑啝�ȉ����͂Ȃ������B�������A�J�L�t���ʂ������e���O�T�̗��D���i�͉��������B
��1�F2015�N25,668kg�A2016�N36,110kg�A2017�N30,486kg�A2018�N36,017kg�A2019�N34,312kg�A2020�N34,209kg�A2021�N11,844kg�A2022�N10,386kg
��2�F�����s������_�ѐ��Y�����Z���^�[HP
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 �ܖ��ɗl�����قȂ�ꍇ������ׁA �ܖ��ɗl�����قȂ�ꍇ������ׁA
�����T���v�����m�F
 ���D���̓��������A ���D���̓��������A
 �W�H�����瓿�����k���Ɩ�勴��]�� �W�H�����瓿�����k���Ɩ�勴��]��
 �W�H�����瓿�����k����]�� �W�H�����瓿�����k����]��
�������k���͉��₩�Ȋ��ł���B
 �W�H���암 �W�H���암
�������k���Ɗ������Ă���B
�ۂ��₪���������B
|
 |
 |
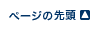 |
 |
|
13�@2022/09/16�@���Q����2����D��
|
|
�@���Q����2����D�9�����{�ɊJ�Â��ꂽ�i9��16���j�B�o�i�ʂ�13,220kg�ƍ�N�������̏o�i�ʂƔ�r����163���ƂȂ����i2021�N���D��F8,114kg�j�B�N�ԏo�i�ʂł�65,725kg�ƍ�N�Ɣ�r����168���ƂȂ����i2021�N�N�ԏo�i�ʁ�39,207kg�j�B����͓����l�����ł����������D��⍂�m�����D��ł̏o�i�ʂ̌X���Ƃ͈قȂ��Ă���i�������E���m���͍�N�Ɠ����܂��͌��Y���Ă���j�B�����l�����ł����Q���͖L�㐅���`���˓��C�ƁA�������⍂�m���̊C��Ƃ͈قȂ�ׂł��낤�B
�@������2015�N����2020�N����100,000kg�`150,000kg���x�o�i����Ă���ׁA���ۂ͗�N�̔������x�̏o�i�ʂƂ�����i��N�x���������Ă����Ƃ������Ƃł���j�B
�@����A���Q�����D��͈��Q�������̊�]��������FAX���D�ƂȂ����B���ׁ̈A���O�ɃT���v���Ɗώ@����𑗂��Ē����A����Ɋ�Â��ăe���O�T�����c�������B���ۑS�Ă̕U���m�F�����킯�ł͂Ȃ����A�Ȃ��Ȃ��ǂ��c�����邱�Ƃ��ł����B
�@���ꂼ��m�F���Ă����ƁA�o�i���������ƃe���O�T�̐���͂悭��v���Ă���A�N�����̃e���O�T���Y��ȉ��N�ł���A�g���N�̖����͐ԑ�����������Ă����B�܂��A�����Y�n�ł��u�t���ɍ̎悵���e���O�T�v�Ɓu�Ċ��ɍ̎悵���e���O�T�v�͕ʖ����ƂȂ��Ă����ׁA�[�����ē��D���邱�Ƃ��ł����B���ɂ͉J�N�ɂ���������Ă���Ǝv����e���O�T�����������A���������ƃT���v���Ŏ��O�Ɋm�F���邱�Ƃ��ł����B���̂悤�ȓw�͂��A�̎�ƎҁA�����A���D�Ǝ҂̊ԂɍX�Ȃ�M���W������Ă����̂ł��낤�B�X�ɗǂ��e���O�T�������o�i����Ă����A�ƊE������������ł��낤�B
�@���D�Ǝ҂�7�ЁB���������D��Ɠ��l�A�ʏ킱�̎����̃e���O�T�̓J�L�t���������Ȃ�A��1����D��������ꂪ������₷���B���������D��Ƃ͈قȂ�_�́A�o�i�ʂ���N��葝���Ă��邱�Ƃł���B�ȏ���A���D���i�̓Z�I���[�ʂ�������Ɨ\�z�A���ہA���D���i�͗������������i�ƂȂ����i�������A���X���D���i�̈��������͑R��������Ȃ������j�B
��1�F2015�N148,834kg�A2016�N118,364kg�A2017�N133,979kg�A2018�N114,332kg�A2019�N103,473kg�A2020�N83,904kg�A2021�N39,207kg�A2022�N65,725kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 |
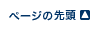 |
 |
|
14�@2022/10/06�@������4����D��
|
|
�@�É�����4����D�10����{�ɊJ�Â��ꂽ�i10��6���j�B�o�i�ʂ�7,988kg�ƍ�N�������̏o�i�ʂƔ�r����86���ƂȂ����i2021�N���D��F9,277kg�j�B10����{���̔N�ԏo�i�ʂł�28,427kg�ƍ�N�Ɣ�r����81���ł���A�N�Ԃ�ʂ��Č��Y�X���ł���i2021�N�N�ԏo�i�ʁ�34,926kg�j�B
�@2015�N����̔N�ԏo�i�ʂł͉ߋ�2�Ԗڂɏ��Ȃ��ʂł���i���j�A�N�X���Y���Ă���ƌ��킴������Ȃ��B��Ă��ɂ��Ƃ��낪�傫�����A���̌����Ƃ��č����̎֍s���l������B�����͒ʏ�A�ɓ��������C�݂Ɍ������ė��ꂽ��A�쉺���Ă������A���ꂪ�����ω�����ƈɓ������A���Ɉɓ��������C�݂̊��ɑ傫�ȉe����^����B���ꂪ���ʂƂ��Đ��Y�ʂɑ傫���e����^���Ă����B
�@�ɓ������ɂ͑O�����肵�Ċe�Y�n�̃e���O�T���m�F�����B�ɓ��������C�݂̒n��ł͎�ɎN�������o�i����A�������g���N1���A�g���N1�����A��g��2���A��g��2�����A�l�X�ł���B�e�X�m�F���Ă����ƁA�e�������ł̓e���O�T�l���ɑR���o���c�L�͂��܂茩��ꂸ�A���q�l�ɓZ�߂ďЉ�₷���Ɗ������B����Ŗ����Ԃł́A�����̍��ȏ�ɗl�����قȂ��Ă���Ɗ������e���O�T���������B������̎�Ǝ҂̔c���̍��ɂ����̂Ǝv���邪�A��X�Ǝ҂������̌��t������Γ��ɖ��͂Ȃ��B�ɓ��������C�݂ł͐ԑ��ŃA�J�A�I��J�L�t�Ƃ������������o�i����Ă������A�R���A�I��J�L�̕t���͏��Ȃ��A���E�N���H����Ώ\���g�p�ł���������������B�̎�Ǝ҂̕��X�̈ӎ��������Ȃ��Ă������Ƃ͔��ɗL�����ƂŗL��A��X�Ǝ҂��ł��邾�������Ă��������Ǝv���B
�@���D�Ǝ҂�7�ЁB11���Ɉɓ����D��͊J�×\��ł��邪�A����o�i�����n��̃e���O�T�ł͂Ȃ��B���ׁ̈A����̃e���O�T����]����ꍇ�͖{���D��Ō�̃`�����X�ƂȂ�B�����āA���Y��O����D��i��3����D��j�ł̍������e�������ׁA�{���D��ł����D���i�͍��������B�����11���ɊJ�Â���A���̓��D��������Ĉɓ��Y�e���O�T�̓��D��͏I������B
��10����{���̗ݐϏo�i��
2015�N89,587kg�A2016�N90,932kg�A2017�N72,001kg�A
2018�N55,917kg�A2019�N38,775kg�A2020�N27,972kg�A
2021�N34,926kg�A2022�N28,427kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 ������E�n���b�N ������E�n���b�N
 ������̗V���� ������̗V����

������̗V��������H�f����
 �{��̃e���O�T�ۊnj� �{��̃e���O�T�ۊnj�
 ��拙�` ��拙�`
���C�݂͔g�������ׁA�e���O�T��������������B
|
 |
 |
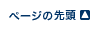 |
 |
|
15�@2022/10/21�@�郖����2����D��
|
|
�@�郖����2����D�10�����{�ɊJ�Â��ꂽ�i10��21���j�B�o�i�ʂ�1,145kg�ƍ�N�������̏o�i�ʂƔ�r����74���ł������i2021�N���D��F1,556kg�j�B�N�ԏo�i�ʂł�2,847kg�ƍ�N�Ɣ�r����77���ƌ��Y���Ă���i2021�N�N�ԏo�i�ʁ�3,682kg�j�B2015�N����̔N�ԏo�i�ʂł͉ߋ�3�Ԗڂɏ��Ȃ��ʂł���i���j�B
�@��1�D���i�͍�N��荂���������A����ɂ��ւ�炸���Y���Ă���Ƃ������Ƃ́i�ʏ�ł���Η��D���i����������ΐ��Y�ʂ͑�������j�A��͂���ۂɊC���ɐ������Ă��Ȃ��̂ł��낤�B�����͍����̑�֍s�ƍl������B�n���I�ʒu���炷��ƁA�ߗׂ̈ɓ�������ɓ��哇�Ƃ͈قȂ����e�����Ă���ƍl���Ă���i���ہA����܂ł͏郖���Y�e���O�T�͓����s�Y�e���O�T�̏o�i�ʂƑ�������X��������ꂽ�j���A���N�͓����s�Y�e���O�T���l�Ɍ��Y���Ă���ׁA�ڍׂȍ����̗����c���������Ƃ���ł���B
�@�������N��葁��11�����D���߂ƂȂ����B�郖���Y�e���O�T�̓A�����n�e���O�T�ł���A�����s�Y�e���O�T�ɋ߂��e���O�T�ł���B�����s�Y�e���O�T��11��17���ɊJ�×\��ł��邪�A���Y�X���Ɨ\�z�����ׁA�{���D��Ŋm�ۂ���X��������ƍl����ꂽ�B���ہA�J�[�����Ƒ�1����D�������������i�ŗ��D���ꂽ�B
��10����{���̗ݐϏo�i��
2015�N2,146�A2016�N4,357kg�A2017�N4,739kg�A2018�N1,565kg�A2019�N3,772kg�A
2020�N4,107kg�A2021�N3,682kg�A2022�N2,847kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 |
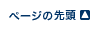 |
 |
|
16�@2022/11/10�@������5����D��
|
|
�@�É�����5����D�11����{�ɊJ�Â��ꂽ�i11��10���j�B�{���D��Ŗ{�N�x�̐É������D��͏I������B�o�i�ʂ�9,080kg�ƍ�N�������̏o�i�ʂƔ�r����91���̌��Y�i2021�N���D��F10,020kg�j�A�N�ԗv�o�i�ʂ�37,507kg�ƍ�N�Ɣ�r����83���̌��Y�ƂȂ����i2021�N�N�ԏo�i�ʁ�44,946kg�j�B2015�N����̔N�ԏo�i�ʂł��ߋ�2�Ԗڂɏ��Ȃ��ʂł���i���j�A�N�X���Y���Ă���ƌ��킴������Ȃ��B
�@�����̎֍s�ɂ����ω��������ƍl�����邪�A����̓I�Ɍ��������A�ڍׂȌ������𖾂���A���Y�̑������\�ł͂Ȃ����Ǝv���i��G�u�����S�̂̕ω��v���u�e�n��E�e�n��̉h�{���E�C�����v�ɗ^����e�����j�B
�@����o�i�����e���O�T�͎�ɏ����c�n��i���ɓ��j�A�m�Ȓn��i���ɓ��j�A�O�Y�n��i���ɓ��j�ł������B��Ԃ͊T�˗ǍD�ŁA�g�����N�͂������A�������N���J�L��ٕ������Ȃ��e���O�T�����������B�܂��ԑ����I�ʂ��\���ɂ���Ă���A�N���H�����ہA�����܂肪�����Ȃ�Ɗ��҂ł����B�����͂�͂莩�R���l�������ƂƂȂ�B����ŁA���ʂł͂��邪�����ƕi�����قȂ�e���O�T����������A����������ł��U�ɂ���ėl�����قȂ�e���O�T���������肵���B���ۂɃe���O�T�����Ă�����D���邪�A�ł���Α����ɂ��Ē����������w����̎�舵�������₷���i���q�l�ւ̏o�ד��j�B
�@�N�Ԃ�ʂ��Č��Y���Ă���A�܂��O����D��ł����Ȃ藎�D�l�����������ׁA�{���D��ł���������\�����l����ꂽ�B�������A������������Ə���₦���މ\��������B�K�v�ʂ��悭�������Č�����̑Ó��ȉ��i�ŗ��D�������B����͑O���D��̗��D�Ǝ҂�������x�m�ۂł����ׂł��낤���A�z����͍������Ȃ������i����ł���N���͉��i���㏸���Ă����j�B����͐V�N��������2023�N2���i�܂���3���j�ɊJ�×\��ł���B
���N�ԗݐϏo�i��
2015�N107,311kg�A2016�N103,488kg�A2017�N85,893kg�A2018�N64,524kg�A2019�N45,506kg�A
2020�N36,404kg�A2021�N44,946kg�A2022�N37,507kg
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 �����c�̃e���O�T�ۊnj� �����c�̃e���O�T�ۊnj�
 �����c�̊C�� �����c�̊C��
 ������̗[�� ������̗[��
 �����̋|���l �����̋|���l
 �O�Y�C�� �O�Y�C��
|
 |
 |
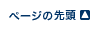 |
 |
|
17�@2022/11/17�@�����s��2����D��
|
|
�@�����s��2����D�11�����{�ɊJ�Â��ꂽ�i11��17���j�B�{���D��Ŗ{�N�x�̓����s���D��͏I���A�܂��S���̓��D����I���ƂȂ�B�o�i�ʂ�7,636kg�ƍ�N�������̏o�i�ʂƔ�r����80���̌��Y�i2021�N���D��F9,549kg�j�A�N�ԗv�o�i�ʂ�14,468kg�ƍ�N�Ɣ�r����85���̌��Y�ƂȂ����i2021�N�N�ԏo�i�ʁ�17,049kg�j�B2015�N����̔N�ԏo�i�ʂł��ł����Ȃ��ʂł���i��1�j�A�N�X���Y���Ă���ƌ��킴������Ȃ��B
�@���n��Ɠ��l�A�����̎֍s�ɂ����ω��������ƍl�����邪�A�C��̉h�{�����������Ă���Ƃ̂��ƁB�����̎֍s�Ɖh�{���ω��Ƃ̊֘A�������ł���A��茴���𖾂Ɍq����̂ł͂Ȃ����B�C�����ω��Ƃ̊֘A�������Ĕ����ł���Ηǂ����Ǝv���B����œ����s�͍��N�����c���Y���������Ă���A���t���{�i���\��Ƃ̂��ƁB����A�������đ��Y���Ē�����Ǝv���B
�@���D���ɓ����ďo�i�����e���O�T���m�F����B��2����D��͒ʏ�A�Ċ��Ɏ��n���ꂽ�e���O�T���o�i�����ׁA�J�L��A�I�������t�����Ă��邱�Ƃ������B�������A����o�i���ꂽ�e���O�T�ɂ̓J�L��A�I�̕t���͏��Ȃ��A�Ǖi�ł������B�Ǖi�ł��邱�Ƃ͖ܘ_�ǂ����A��͂�C�m������ω����Ă��邩������Ȃ��i�J�L�̕t����A�I�̕t���͉h�{���������A�C�����������ꍇ�ɔ�������j�B
�@�����s���D��ŏo�i�����e���O�T�̓A�����n�̑����e���O�T�ő��n��ł͂��܂�o�i����Ȃ��B���ɎN�e���O�T�͎�ɉ��N�ł���ׁA���l�̂���e���O�T�ł���i��2�j�B�����������w�i�ƌ��Y����A�O��̓��D��ł͑S�̓I�ɍ��l���D�ƂȂ�A�{���D��ł����̌X���������đO��ȏ�̍��z���D�ƂȂ����B�{���ʂ����N�x�̎��n�ʂ̑����Ɍq����Ηǂ����A���������͏���̗₦���݂Ɍq����\��������B�ƊE�Ƃ��Ă��Ó��ȉ��i�ŗ��D���Ă����Ǝv���B
��1�F�N�ԗݐϏo�i��
2015�N36,163kg�A2016�N24,498kg�A2017�N30,789kg�A2018�N28,007kg�A2019�N30,285kg�A
2020�N35,828kg�A2021�N17,049kg�A2022�N14,468kg
��2�F���N�e���O�T�F�̎�シ���ɎN���H����Ɖ��N�ƂȂ�B
�@�@�@���N�͍̎�Ǝ҂����{���邱�Ƃ������ׁA���N�͊ł���B
�@�@�@�{�e���O�T�Ńg�R���e��������Ɠ����ȃg�R���e���ƂȂ�B
�N�e���O�T�F�̎��A���N�ȏ�ۊǂ�����A�N���H�����e���O�T�B
�@�@�@�{�e���O�T�Ńg�R���e��������ƁA�݂��������g�R���e���ƂȂ�B
�i�^���@�X�c���G�j
|
 |
 �o�i�����e���O�T �o�i�����e���O�T
�i�����s���A���Y�����Z���^�[���j
 ���D��� ���D���
�i�����s���A���Y�����Z���^�[���j
 �����s���A���Y�����Z���^�[�͋��l���ɗ��n�B �����s���A���Y�����Z���^�[�͋��l���ɗ��n�B
|
 |
 |
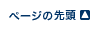 |
|
 |
 |